
- お木曳車 特大
- 価格:98,600円(税込)
▼ 商品説明の続きを見る ▼
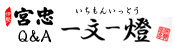 いただいたご質問にお答えしている、 “宮忠Q&A 一文一燈”もご覧ください。 | 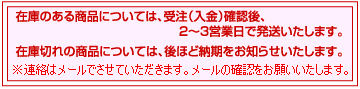 |
こちらの商品は、店頭でも販売いたしております。
在庫状況はすぐ反映するよう努めておりますが、売切れの場合はご容赦ください。
商品写真の色合いは、お客様がお使いの情報端末デバイスの環境により若干異なって見える場合がございます。
価格:98,600円(税込)
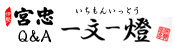 いただいたご質問にお答えしている、 “宮忠Q&A 一文一燈”もご覧ください。 | 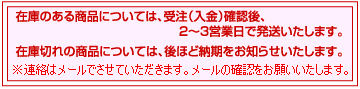 |
こちらの商品は、店頭でも販売いたしております。
在庫状況はすぐ反映するよう努めておりますが、売切れの場合はご容赦ください。
商品写真の色合いは、お客様がお使いの情報端末デバイスの環境により若干異なって見える場合がございます。
価格:98,600円(税込)